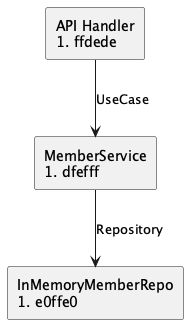Vibe Coding実践完全ガイド──AIに指示してコードを書かせる設計対話型開発法
序章:「Vibe Coding」とは何か?なぜ今必要なのか
2025年現在、「Vibe Coding」という新しい開発スタイルが急速に普及しつつあります。
もはや「コードは人が一行ずつ書くもの」ではなくなりつつある現場。
AIが“人の意図”を受けて、自律的に設計・実装・レビューまで行う時代が到来しました。
このガイドでは、Vibe Codingの思想・流れ・現場での使い方・AIとの設計対話の実践法を、徹底的に分かりやすく・現実的に整理します。
1. Vibe Codingとは──思想と特徴
■ 概念の整理
Vibe Codingとは、「実装を書かず、AIに自然言語で指示(プロンプト)を出し、コードを“生成・設計”してもらう」開発手法です。
- プロンプト=新しい設計言語
- 実装はAI(Copilot、Claude、Cursorなど)が担当
- 人間は「何をなぜ作るのか」「どんな依存・責務・ドメインか」を言語化し、設計対話を重ねる
■ どこが従来と違うのか
- 実装“自体”ではなく、「設計・意図・構造」を自然言語で伝える点
- 実装・リファクタ・テスト生成もAIが担う(Copilot Workspace等の自動化)
- 人は設計者・レビュワー・プロンプターに集中
■ Andrej Karpathy提唱──「コードを書くのではなくAIに“感じさせる”」
Karpathy氏はVibe Codingを「AIに意図・設計・空気感(Vibe)を伝える技術」と定義しています。
プログラマーの役割は「設計意図・依存・将来像の言語化」そのもの。
2. Vibe Codingの実践プロセス──設計対話の流れ
【1】要件・仕様の自然言語化
まず、「どんな機能がほしいか」「どんな制約があるか」を、人間がプロンプトとして記述します。
要件は曖昧NG、具体的・文脈豊かな表現を心がけます。
“ユーザーが商品をカートに入れるECサイトのショッピングカート機能。
カートは商品IDと数量を保持し、ログイン中のユーザーごとに管理。
商品追加・削除・カート内容取得APIをGo言語で実装したい。
テスト可能な設計・責務分離で。”【2】AIに設計の骨子・依存関係を問う
- どんなデータ構造が適切か?
- どの層がどの責務を持つべきか?
“どのような構造体・インタフェース設計が適切か?
ドメイン層とAPI層の責務分離、永続化はインメモリでOK。テスト容易性重視。”【3】AIから設計案・雛形コードをもらい、設計意図を明確化
AIが出力する設計・実装案を人間が評価し、「なぜそうなるか」を明文化。
役割・責務・依存関係を図式化してもよい。
【4】細部のリファクタ・命名改善もAIに反復依頼
- 名前が曖昧な箇所や、ユースケース漏れに着目
- 追加仕様も自然言語で伝える(「こういうエッジケースも想定して」)
【5】テスト・レビューまでAIを活用
- 単体テストコードもプロンプトで生成依頼
- AIレビュー→人間が理由・設計意図を補足
3. Vibe Codingの現場効果──なぜ現場で使われているか
■ 効果・メリット
- 実装速度2〜5倍
- 設計意図・仕様伝達コストの大幅削減
- リファクタ・テスト生成がAIで一貫
- 設計レビューの網羅性向上(AIが観点抜けを指摘)
- “コーディング”から“設計対話”へ役割移行
■ 現場からの実例
- YC 2025バッチでは「AI主導コードベース」がプロダクトの25%以上
- VisaやReddit等の大企業でも、「AIリーディングスキル」を採用要件化
- スタートアップの開発チームで「設計対話を毎日SlackでAIとやる」事例も
4. 実践編──Vibe Codingのプロンプト・レビュー演習
◇ ケース1:APIサービスのVibe Coding
要件を自然言語で記述
“顧客が登録・検索できるシンプルな会員管理APIをGoで。
永続化はインメモリでOK、会員ID・名前・メールアドレス管理。
登録・検索・削除API、単体テスト付き。”AIへのプロンプト実例
“インタフェース設計、構造体設計、各APIの責務分離、テストコードの雛形まで一括生成して。
エラー設計・バリデーションも意識して。”AIが出力するコード例(Go)
type Member struct {
ID string
Name string
Email string
}
type MemberRepository interface {
Create(m *Member) error
FindByID(id string) (*Member, error)
Delete(id string) error
}
type InMemoryMemberRepo struct {
data map[string]*Member
}
// 実装略コードレビュー観点(AI→人コメント)
type InMemoryMemberRepo struct {
data map[string]*Member
}
@Reviewerdataのスレッドセーフ性が考慮されていません。複数ゴルーチンからの同時アクセスに備え、sync.RWMutex等のロックを導入してください。
Vibe Codingでも、AIの設計案を「なぜこうなっているか?」と理由ごと読解し、必要なら補正することが重要です。
◇ ケース2:ドメイン駆動設計のVibe Coding演習
プロンプト例
“決済ドメインの支払い処理ユースケースをTypeScriptで。
責務分離(ドメインサービス/エンティティ)、例外設計、外部決済APIラッパーの抽象化も意識して。”AIが出す設計案に「なぜ?」を重ねていく
- なぜここでインターフェース切っているのか
- どこに業務ロジックを閉じ込めているのか
- 型安全性、例外伝搬の流れは妥当か
コードレビュー例
class PaymentService {
process(paymentRequest: PaymentRequest): PaymentResult {
// 省略
}
}
@ReviewerPaymentServiceが外部APIラッパーの詳細(APIキー、タイムアウト等)まで直接保持しています。責務を分離し、外部依存はAdapter層に集約しましょう。
ドメイン設計では「どこに依存を持たせるか」「なぜその責務分離か」を常にAIと対話しながら調整します。
◇ ケース3:AIレビュー+人レビューの併用演習
プロンプト例
“上記コードのテストケース・カバレッジ不足、潜在的な副作用がないかチェックして。設計意図が不明瞭な箇所があれば、理由ごと指摘して。”AIのレビュー指摘
- テストカバレッジが不足
- 命名が曖昧
- スコープを縮められる変数
人間が加えるべき補足コメント
- なぜその命名が不十分か
- なぜ副作用が起こる可能性があるか
- ドメインモデル・依存関係設計が現場要件に合っているか
5. Vibe Codingの“やってはいけない”ポイント
■ 要件が曖昧なまま丸投げしない
- AIは具体的な要件・制約・背景情報がなければ「汎用的すぎる実装」を返す
- 「こういうエッジケースも考えて」など具体化が必須
■ “いい感じでやって”は禁句
- 「いい感じ」は人間ならニュアンスで通じてもAIには曖昧
- 「テスト容易性」「トランザクション制御」「依存逆転」など具体単語を入れる
■ 責務分離・依存関係をAI任せにしない
- AIはよく「Service」「Manager」「Util」など汎用的な層を作るが、現場要件を意識しないと破綻しやすい
■ AI出力を盲信しない
- なぜその設計か?なぜその責務分離か?「なぜ」を必ず問い直す
- コードレビュー・設計レビューを“必ず人間が補足”
6. Vibe Codingのプロンプト設計術
■ 良いプロンプトの特徴
- 要件・背景が具体的である
- ドメイン語彙・用語を明確にする
- 責務・依存関係・非機能要件(例:性能・可用性)も指示
- 出力例・NG例も入れると精度UP
プロンプト例(良い例)
“ユーザー登録APIをGoで。バリデーションは外部パッケージで。テストコード付きで。
例:ユーザーIDはUUID、メールはRFC準拠チェック。バリデーションエラー時は400返却。将来MySQL化を想定したインタフェースで。”プロンプト例(悪い例)
“ユーザー登録API作って”■ 「設計対話」をプロンプトに仕込む
- どの層がどの責務を持つべきか
- ドメインルールの優先順位
- 外部サービスとの依存関係の制御
- テスト容易性(DI、モック化設計)
7. Copilot Workspace/Claude 3でのVibe Coding活用例
■ Copilot Workspaceの流れ
- 自然言語で「仕様」「背景」「期待する動作」記載
- AIが設計案+コードを自動生成(PullRequest単位)
- AIレビュー→人がWhyをコメントで補足、設計意図の明文化
- PRの説明文もAIが要約・自動記述
- Merge→次タスク化までAIエージェントで流す
■ Claude 3/Cursorによる「設計対話」の演習
- Claudeは「なぜこう設計したのか?」に理由まで答えやすい
- 「この設計をDDD的に分割し直して」「依存逆転にして」等、具体設計対話が可能
8. Vibe Coding設計観点・レビュー観点チェックリスト
9. まとめ──Vibe Codingは「設計対話」の時代へ
AIが“正解”を出す時代、現場で評価されるのは「何をなぜ作るか」をAIに的確に伝え、「出てきた設計・実装の意味」を深く読み解き・補足できる人間です。
- コードを書かせるのはAI
- 設計意図・責務分離・依存のコントロールは人間
- Vibe Codingとは「設計と実装の対話をAIと協働する」技術
あとがき
この記事ではVibe Codingの思想から実践法、レビュー演習まで一気通貫で解説しました。
本記事を参考に、「AIとの設計対話力」を磨き、現場で活きるエンジニアリングを実現してください。
付録:Vibe Codingプロンプトテンプレ・演習素材
◇ プロンプトテンプレ例
“(ドメイン説明)
(仕様・非機能要件)
(実装言語・設計観点)
(テスト・レビューも依頼)
例:
“サブスクリプションサービスのプラン管理API。
プランID・価格・有効期間を管理し、追加・更新・取得・削除APIをGoで。
テスト・エラー設計も重視、拡張性も考慮。”
”◇ 設計観点リスト
- ドメインモデル/責務分離
- 依存逆転/インタフェース設計
- テスト容易性/モック設計
- 例外・エラー設計
- 拡張性/APIバージョン管理